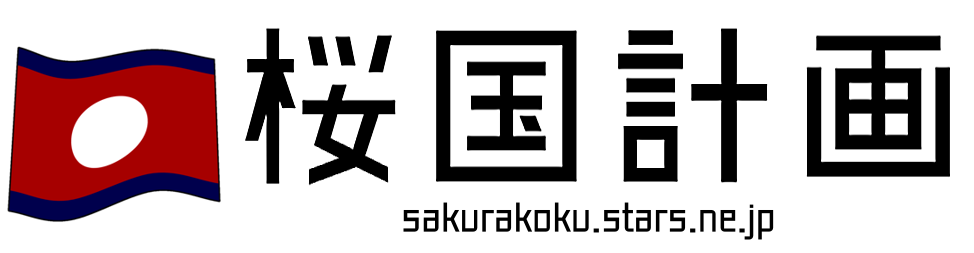目次
前文
第一章 太皇(第一条―第七条)
第二章 国家安全保障(第八条―第八条の三)
第三章 国民の義務と権利(第九条―第三十四条)
第四章 内閣(第三十五条―第四十二条)
第五章 国家議会(第四十三条―第五十五条)
第六章 司法(第五十六条―第五十八条)
第七章 財政(第五十九条)
第八章 地方自治(第六十条―第六十二条)
第九章 緊急事態(第六十三条・第六十四条)
第十章 改正(第六十五条)
第十一章 最高法規(第六十六条)
(前文)
桜国は、長きにわたる歴史と特有の文化を持ち、国民結束の象徴である太皇を戴く国家であり、国民主権の下に立法、行政及び司法の公正な三権分立に基づき統治される。
我が国は、先の大戦による荒廃や多岐に渡る災害を乗り越え、発展を続け、今や世界において主要な地位を占めており、平和主義の下世界各国との友好関係を増進し、世界の永続的な平和に貢献する。
桜国民は、自国と郷土に誇りを持ち、自らの国を守り、基本的人権を尊重するとともに、家族や社会全体を互いに信じ合い、助け合うことで国家を形成する。
我々は、先人が築き上げた自由と規律を重んじるとともに、美しい国土と自然を守りつつ、教育や科学技術、文化の発展に貢献し、活力ある経済活動を通じて国を成長させる。
桜国民は、我々の国家の良き伝統を末永く子孫に継承るため、ここに新しい憲法を制定する。
第一章
第一条(太皇)
太皇は、桜国の君主であり、桜国及び国民結束の象徴であって、主権を有する全国民の意思に基づくものである。
第二条(皇室の伝承)
太皇は、世襲のものであって、国家議会の決めた皇室典範の定める ところにより、これを継承する。
第三条(国旗及び国章・国歌)
国旗は、日昇旗とし、国章を日輪章、国歌は青き山河とする。桜国国民は、いかなる時も国旗及び国歌を尊重しなければならない。
第四条(元号)
元号は、法律の定めるところにより、皇室の継承があった場合のみ制定する。
第五条(太皇の機能)
太皇は、この憲法に定める国事行為のみを行い、国政に対する権能を保持しな い。
第六条(太皇の国事行為)
太皇は、国民のために、国家議会の指名に基づいて桜国の長である首相を任命し、内閣の指名に基づいて最高裁判所の長である裁判官を任命する。
太皇は、国民のために次に掲げる国事に関する行為を執り行う。
一 憲法改正、法律、政令、条約を交付すること。
二 国家議会を召集すること。
三 衆評院を解散すること。
四 儀式を行うこと。
五 衆評院議員の総選挙及び参評院議員の通常選挙の施行を公示すること。
六 国務大臣及び法律の定めるその他の公務員に任免を認証すること。
七 大赦、特赦、減刑、刑の施行の免除及び復権を認証すること。
八 栄典を授与すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること
十 全権委任状並びに大使館の信任状並びに批准書及び法律の定めるその他の外交文章を承認すること。
太皇は、法律の定めるところにより前二条の行為を委任することができる。
太皇の国事に関する全ての行為には、内閣の進言を必要とし、内閣がその責任を負う。ただし、衆評院の解散については首相の進言による。
第一項並びに第二項に掲げるもののほか、太皇は、国又は地方自治体、その他
の団体が主催する式典への出席、その他の公的な行為を行う。
第七条(摂政)
皇室規範の定めるところにより、摂政を置くときは、摂政は太皇の名で、国事に関する行為を行う。
第二章 国家安全保障
第八条(平和主義)
桜国民は、平和的で最低限度の国防義務を有し、正義と秩序を基に国際平和を誠実に追求する。国権の発動としての戦争を放棄し、武力威嚇及び武力行使は世界の紛争を解決する手段として用いない。
防衛軍
第八条の二、我が国の平和主義の維持と独立並びに国家及び国民の安全を維持するため防衛軍を保持する。防衛軍の最高指揮者は防衛大臣とする。
防衛軍が任務を行う際には、法律の定めるところにより国家議会の承認、その他の統制に服する。
防衛軍は法の定めるところにより、国際平和と我が国の永続的な安全を確保するため、国際的に協力して行われる活動及び公的秩序を維持し、国民の生命及び自由を守るための活動ができる。
防衛軍の組織、統制、機密保持に関する事項は法律で定める。
領土の保全
第九条の三、国は独立と主権を維持するため、国民と協力し、領を守り、その貴重な資源を確保しなければならない。
国家警察委員会
第八条の三、国家警察委員会は公的秩序を維持し、常に国の平和に寄与しなければならない。
国家警察委員長は、国家の長である首相によって指名される。主に内閣の解散によってその職務を完遂する。
国家警察委員会の機能、権限、および運営に関する具体的な事項は法律で定める。
第三章 国民の義務と権利
第九条(桜国民)
桜国民の要件は、全て法律で定める
第十条(国民の責務)
この憲法が国民に保障する自由と権利は、国民の努力により、保持され続けなければならない。自由及び権利には、責任及び義務が伴うことを自覚し、常時公的秩序に反してはならない。
第十一条(個人としての尊重権)
全ての桜国民は、個人として尊重され、生命の自由、幸福実現に対する国民の権利については、公的秩序に反さない限りは、立法及びその他の国政の上で、最大限尊重されなければならない。
第十二条(法の下の平等)
全ての桜国民は、法の下の平等であって、人種、信条、性別、障害の有り無しに関わらず、社会的な身分、政治的、または社会的関係において差別があってはならない。
大十三条(公務員の選定及び罷免に関する権利等)
公務員を選定、罷免することは、主権を持つ国民の権利である。全ての公務員は社会において全体への奉仕者であって、一部への奉仕者ではない。
一 公務員の選定を選挙により行う場合は、桜国籍を有する成人による普通選挙の方法で行う。
二 選挙における投票の秘密は、侵されてはならない。選挙人は、その選択に関し、公的にも私的にも責任を問われてはならない。
第十四条(請願をする権利)
損害の救済、公務員の罷免、命令若しくは規則の制定、その他の事項に関し、平穏に請願をする権利を持つ。請願をした者は、いかなる差別や待遇も受けてはならない。
第十五条(国等に対する賠償請求権)
公務員の不法行為によって損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国または地方自治体に、その賠償を求めることができる。
第十六条(身体の拘束及び苦役からの自由)
桜国民は、いかなる社会的関係においても、身体を拘束されてはならない。
第十七条(思想の自由)
思想の自由は、保障する。
第十八条(個人情報の不当利用の禁止)
個人に関する情報を不当に利用し、保有してはならない。
第十九条(信仰の自由)
信仰の自由は、保障する。国又は地方自治体は、いかなる宗教団体に対しても、特権を与えない。
第二十条(宗教活動に参加することを強制してはならない)
特定の宗教のための活動を強制してはならない。
第二十一条(表現の自由)
表現の自由は、保障する。公の秩序を害することを目的とした活動を行ってはならない。
第二十二条(国政行為の説明責務)
国政行為は国民に説明する責務がある。
第二十三条(職業選択の自由)
すべての国民は居住、職業選択の自由を有する。外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を有する。
第二十四条(学問の自由)
学問の自由は、保障する。
第二十五条(家族、婚姻等に関する基本原則)
家族は、社会の基礎的な概念として、共に助け合い、尊重されなければならない。
一 婚姻は、両性の合意に基づいて成立し、夫婦が同等の権利を持つことを基礎として、相互的な協力により、維持されなければならない。
二 家族、婚姻及び財産権、離婚、相続、親族に関するその他事項に関してはそ法律が定める。
第二十六条(生存権等)
桜国民は、健康かつ文化に満ちた最低限の生活を営む権利を有する。国は、国民生活のあらゆる側面において、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
第二十七条(環境保全の責務)
国又は地方自治体は、国民と協力して、互いに良好な環境を持つことができるように保全に努めなければならない。
第二十八条(在外国民の保護)
国は、国外において緊急事態が生じたときは、在外国民の保護に努めなければならない。
(公平な教育と義務等)
第二十九条 桜国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて公平な教育を受ける権利を有する。
一 桜国民は、法律の定めるところにより、その保護する子に普通教育を受けさせる義務を負う。なお、義務教育は無償とする。
二 教育は国の将来になくてはならないものであり、国は教育環境の整備に努めなければならない。
第二十九条(労働の権利)
桜国民は、労働の権利を有し、義務を負う。最低賃金、就業時間、勤労条件、休息関する基準は、法律で定める。
第三十条(労働者の団結権)
全ての労働者は、団結する権利、団体行動を行う権利を有する。
第三十一条(財産権)
財産権は保障する。財産権については、法律で定めるものとする。この場合において知的財産権は、国民の知的創造力の向上に資するように配慮しなければならない。
一 私有財産は、正当な補償の下に、公共のために用いることができる。
第三十二条(納税の義務)
桜国民は、納税の義務を負う。
第三十三条(裁判権)
裁判所において裁判を受ける権利を有する。
第三十四条(逮捕に関する手続の保障)
現行犯逮捕の場合を除いては、裁判官が理由となっている犯罪を明示しなければ、逮捕されない。
第四章
内閣
第三十五条(内閣と行政権)
行政権は、この憲法の特別な定めのある場合を除いて内閣に属する。
第三十六条(内閣の構成及び国家議会に対する責任)
内閣は、法律の定めるところにより、その首長である内閣総理大臣、その他の国務大臣で構成される。
一 内閣総理大臣及び国務大臣は、現役の軍人であってはならない。
二 内閣は行政権の行使について、国家議会に対し連帯責任を負う。
(内閣総理大臣の指名及び衆評院の優越)
第三十九条 内閣総理大臣は、国家議会議員の中から国家議会が指名する。
一 衆評院と参評院とが異なった指名をした場合において両議院の意見が一致しないとき、若しくは衆評院が指名をした後五日以内に参評院が指名をしないときは、衆評院の指名を国家議会の指名とする。
(国務大臣の任免)
第三十七条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。国務大臣は過半数が、国家議会議員でなければならない。
一 内閣総理大臣は、任意で国務大臣を罷免することができる。
第三十八条(内閣の不倍任と総辞職)
内閣は、衆評院が信任の決議案を可決したときは、十日以内に衆評院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
第三十九条(内閣総理大臣が欠けた時の内閣総辞職等)
内閣総理大臣が久けたとき、又は衆評院議員総選挙の後に初めて国家議会の召集があったときは、内閣は総辞職をしなければならない。
一 内閣総理大臣がけたとき、若しくはこれに準ずる事態が発生した場合、法律の定めるところにより、内閣総理大臣が予め指定した国務大臣が、臨時代理としてその職務を行う。
第四十条(総辞職後の内閣)
総辞職後の内閣は、新たに内閣総理大臣が任命されるまでの間、いかなる政治的空白を避けるためにその職務を行わなければならない。
第四十一条(内閣総理大臣の職務)
内閣総理大臣は行政を指揮監督し、総合的に調整を行う。
一 内閣総理大臣は内閣を代表して、議案を国家議会に提出し、並びに国務及び外交関係について国家議会に定期的に報告する。
二 内閣総理大臣は、最高指揮官として、首都防衛前線を統括する。
第四十二条(内閣の職務)
内閣は、他の一般事務のほか、次に掲げる事務を行う。
一 法律を執行し、総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。
四 法律の定める基準に従い、国の公務員に関する事務をつかさどること。
五 予算案及び法律案を作成して国家議会に提出すること。
六 法律に基づいて、政令を制定すること
第五章
第四十三(国家議会と立法権)
国家議会は、国権の最高機関であって、国家唯一の立法機関である。
(両議院では)
第四十四条 国家議会は、衆評院院及び参評院の両議院で構成する。
(両議院の組織)
第四十五条 両議院は、全国民を代表する選挙された国家議会議員で組織する。
一 両議院の定数は、法律で定める。
第四十六条(選挙人の資格)
両議院の選挙人の資格は、法律で定める。
第四十七条(衆評院議員の任期)
衆評院議員の任期は、三年とする。ただし衆評院が解散された場合には、期間満了前に終了する。
第四十八条(参評院議員の任期)
参評院議員の任期は、六年とする。ただし、二年ごとに議員の半数を改選する。
第四十九条(選挙に関する事項)
選挙区、投票方法、その他両議院の議員の選挙に関する事項は法律で定める。
第五十条(議員兼職の禁止)
同時に両議院の議員となることはできない。
第五十一条(議員の不逮捕特権)
両議院の議員は、国家議会の会期中は逮捕されない。
第五十二条(議員の免責特権)
両議院の議員は、議院で行った演説、討論について、院外で責任を問われない。
第五十三条(通常国家議会)
通常国家議会は、毎年一回召集される。
第五十四条(臨時国家議会)
内閣は、臨時国家議会の召集を決定することができる。総議員の四分の一以上の要求があったときは、その日から二十日以内に臨時国家議会が召集されなければならない。
第五十五条(政党)
国は、政党が民主主義に不可々の存在であり、その活動の公正な発展に努めなければならない。
一 政党における活動の自由は、保障する。
二 政党に関する事項は、法律で定める。
第六章
司法
第五十六条(司法所と司法権)
全て司法権は、最高司法所及び法律の定めるところにより設置する下級司法所に属する。
一 全て司法官は、その良心に従い、独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。
第五十七条(最高司法所の規則制定権)
最高司法所は司法に関する手続き、弁護士及び司法所の規則を定める権限を有する。
一 司法に関わる者は、最高司法所の定める規則に従わなければならない。
二 最高司法所は、下級司法所に関する規則を定める権限を、下級司法所に委任することができる。
第五十八条(公開の法定)
裁判の弁論及び手続並びに判決は、公開の法廷で行う。
第七章
財政
第五十九条(財政の原則)
国の財政を処理する権限は、国家議会の議決に基づいて行わなければならない。財政の健全性は、法律の定めるところにより確保されなければならない。
第八章
地方自治
第六十条(地方自治体)
地方自治体の組織及び運営に関する事項は、法律で定めるものとする。
第六十一条(地方議会)
地方公共団体には、法律の定めるところにより、議会を設置する。
一 地方自治体の長、議会の議員は、その地方自治体の住民が、直接選挙する。
第六十二条(地方自治体の財産)
地方自治体は、その財産を管理、事務で処理し、
一 地方自治体は行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
第九章
緊急事態
第六十三条(国家緊急令)
内閣総理大臣は、我が国に対する武力攻撃、内乱による社会的秩序の混乱、地震等の大規模災害、テロリズム等の事件等、その他法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるとき、法律の定めるところにより、閣議にかけて国家緊急事態を宣言することができる。
一 国家緊急令は、法律の定めるところにより、事前又は事後に国家議会の承認を得なければならない。
二 内閣総理大臣は、不承認の議決があったとき、国家議会が国家緊急令の解除を議決したとき、若しくは継続する必要がないと認めるときは、法律の定めるところにより、宣言を速やかに解除しなければならない。
第六十四条(国家緊急令の効果)
国家緊急令が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同程度の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要としない支出の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。
一 前項の政令の制定及び処分については、法律の定めるところにより、事後に国家議会の承認を得なければならない。
二 この宣言が発せられた場合には、法律の定めるところにより、国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して、公の機関の指示に従わなければならない。
国家緊急令の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、議院は解散されない。
第十章
第六十五条(改正)
第百条 この憲法の改正は、国家議会の総議員の過半数の賛成で国家議会が議決し、国民に提案してその承認を得なければならない。
この承認には、法律の定めるところにより、国民投票において過半数の賛成を必要とする。改正について前項の承認を経たときは、太皇は、直ちに憲法改正を公布する。
第十一章
最高法規
第六十一条(憲法の最高法規)
この憲法な、国の最高法規であって、桜国民は、この憲法を尊重しなければならない。内閣総理大臣、国務大臣、国家議会議員、裁判官その他公務員は、この憲法を擁護しなければならない。
(施行期日)
この憲法改正は、成和七年三月八日から施行する。